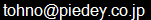|
||||||
|
高機動型MARK-Iファイターの量産開始は、必然的にパイロットとなるハイパーアンドロイドつまりハイプの増産をもたらした。パイロットがいなければ戦闘機も能力を発揮できないからだ。 その結果として、オルランドの男女比率はほぼ1:1から急速に女性過剰へと傾いていった。オルランドの不死の男達は数が増えることはなかったが、彼らを慰めるために作られたハイプはいくらでも量産可能だったからだ。そして、男達を慰める役目を放棄できない以上、『小雀』と呼ばれたパイロット用のハイプは生産量の増大で充当するしかないのである。 このような状況を、当初は誰も問題だとは認識していなかった。オルランドの男が慰めにハイプを必要とする状況は認識されていたが、ハイプが慰めに男を必要とする状況は誰も想定していなかったのだ。だが、それは最初の本格的な『小雀』だけの戦闘機隊が編成された時点で早々に露呈した。 2Kクラスのバトルクルーザー『ジャンヌ・ダルク』は艦隊防空の専任艦として、通常であれば搭載される攻撃用のアタッカーを一切搭載せず、そのための搭載スペースにも全て戦闘機を搭載していた。 この艦の搭載戦闘機を高機動型MARK-Iファイターに入れ替えるということは、必然的に全パイロットが小雀に入れ替わることを意味した。そもそも艦本体の運用にはそれほどの人数は必要とされず、機体の整備やメンテナンスも自動化されていたので、そのための人員もそれほど多くはなかった。その結果、艦内の男女比は1:10.7という極めていびつな比率に陥った。 そして、艦隊の防空というストレスの貯まる任務に従事しながら、男という癒しを得られない多くの小雀たちを生み出してしまった。 その事実をオルランド皇帝が知ったのは、ドクターキガクと酒を飲んでいる時だった。 「小雀の第1世代、ファーストジェネレーションと呼んでいるがね」とキガクは言った。「彼女らは、小雀戦闘機隊の指揮官層に就任しているわけだが、彼女らが熱心に言うのだよ。戦闘機に男の人格を与えて欲しいと」 「男の人格ね……」と皇帝は答えた。 「小雀たちは自分が乗っている機体に男性を感じることが多いそうだ。まあ情報伝達系の回路を接続するために男性器のような形の道具を挿入させているのは事実だがな」 「キガク。君がそういう設計をした時点で、君自身も戦闘機を男に見立てていたのではないかね?」 「見立てるだけなら、だな」 「というと?」 「戦闘機に男の人格を与えたら、それは見立てではなく、男そのものになってしまう」 「なるほど」 「小雀と機体が充足関係を構築してしまったら、オルランドというシステムから離脱してしまうかもしれない。それはあまり喜ばしい事態とは言えない」 「かといって、このまま座視して放置するのも良くないな。小雀たちの反発を買いかねない。そして、我々は小雀たちの高機動型MARK-Iファイターに勝てる戦闘機を持っていない」 「ではどうするのだ?」 「彼女らの大多数は男を知らない。だから男に夢を見られるのだ。本当の男を見たら幻滅するさ」 「しかし、男の数が足りないのは事実だぞ」 「キガク、彼女らの望む通り、男の人格を持つ高機動型MARK-Iファイターの試作機を作ってやれ。ただし、ストーカーのように偏執的に、男の欲望に忠実に性欲をむき出しにするような人格をな」 「なるほど。ストーカーのようにね」 キガクは嬉しそうにニヤリと笑った。 かくして、ストーカーのように、を隠しテーマとしてキガクの指揮により「ストーキング ファイター」と呼ばれる派生型機体の試作が開始された。 新型の初飛行のテストパイロットは、元皇帝の愛人であるSSNのアヤであった。 アヤが事前に聞いた話は、戦闘機が男の人格を持っているということだけだった。他は全て高機動型MARK-Iファイターと同じだという。SSNの任務の都合で高機動型MARK-Iファイターの飛行訓練も受けているアヤは、小雀ではなかったが問題なくその機体を飛ばすことができた。だから、何の危惧もしていなかった。 アヤは、薄手のハイレグ レオタード状のパイロットスーツを着込んで、機体が待つハンガーに向かった。模倣された物質から構成されるハイプは本質的に破壊されることがないし、真空中で死ぬこともないので、重装備型のパイロットスーツは必要がないのだ。 だが、いざ乗り込もうとしたアヤは絶句した。パイロットが腰を下ろすべきシートが、男の顔の形をしていたのだ。しかも、その顔が好色そうにニヤリと笑って言った。 「やあ。最初の相手が君のような美人で嬉しいな。さあ、僕の顔の上に座ってくれ」 もちろん、百戦錬磨のアヤはその程度のことで逃げ出したりはしない。 アヤは顔の上に平然と座って発艦手順を開始した。 顔もおとなしく黙っていた。 予定された手順通り、機体はバトルクルーザーの側面発進口のカタパルトで押し出され、宇宙空間に飛び出した。 予定された点までそのまま飛行し、そこで折り返して帰還する予定になっていた。 やがて母艦は背後に小さくなり、見えなくなった。 そこでやっと股間の下にある顔がしゃべり始めた。 「やれやれ。そろそろいいかな」 「あら、やっとお喋りを始める気になった?」 「そうさ。お喋りもするが、おしゃぶりもするぞ」 そして顔が口を開き、舌を延ばしてアヤの股間を舐め上げた。 「ひぃっ!」と思わずアヤは悲鳴を上げた。 「うーん、いい味だ。臭いも最高!」 顔はクンクンと股間を嗅ぎ回った。 顔はシートそのものであり、身体はベルトで固定されているので、アヤは逃げることができない。 「おっぱいも揉み心地良さそう」 いきなりシートの背後から2本の手が出てきて、アヤの両乳房を揉み始めた。 「ちょっ、やめて!」 「おお! この感触も最高だ!」 更に顔は言った。 「おや。僕の唾液ではない液体の味や臭いも感じるぞ。これは汗かな?」 「そ、それは……。ち、違うわっ」 そして、まるで勃起するように情報伝達インターフェースがせり上がってきた。これを秘所に挿入することは、この機体の全性能を発揮させるための通常手順であり、アヤもそれを何回も受け入れている。だが、明らかにこの機体はその意味合いが違っていた。 それは、機体が持つ男の醜い性欲が女を征服する証として望む、陵辱装置なのだ。 アヤはやっと自分がテストパイロットとして選ばれた理由を理解した。他の多数の小雀たちであれば、おそらくこのテストに耐えられない。 予定通りの時間にアヤと試作機は帰還した。快楽に紅潮した肌、汗や汗ではない液体に濡れたパイロット服でアヤはキガクに報告を行った。 「おそらくほとんど全ての小雀はこの機体に耐えられないでしょう。それほどにスケベ過ぎます。これを喜ぶのは真性のド変態だけです」 「つまり、君は喜んだということかね?」とキガクはニヤニヤと質問した。 アヤはキガクの顔を強く叩くと、一分の隙もない敬礼を行って、説明を聞くこともなく退出した。 むろん、この結果はキガクと皇帝の望むところだった。 さっそく、このストーキング ファイターは限定的に量産され、バトルクルーザー『ジャンヌ・ダルク』の小雀戦闘機隊に送り込まれた。もちろん、従来型と自由に選択して使って良い、という条件を付けてのことだった。 すぐに悲鳴を上げて突き返してくる、と予想したキガクと皇帝は、自分の考え違いを思い知らされることになった。 なんと大多数の小雀はストーキング ファイターを選び取ったというのだ。 あらためてキガクと皇帝はアヤを呼び出して問いただした。 「なるほど。そういう意図で作った機体だったのですか……」とアヤはため息をついた。「なら失敗作ですね。計画そのものが、女をなめすぎてます」 そう言われると言い返せないキガクと皇帝であった。 だが、この事態は明らかに放置しておくわけにはいかなかった。戦闘出撃が変態デートそのものになるような事態を、軍の規律は放置できないのだ。しかし、皇帝の勅命で「望めば乗って良い」と言ってしまった手前、簡単に撤回もできない。 だが、話は更に急転直下した。 小雀ファースト ジェネレーションの第1世代パイロット達が揃って全てのストーキング ファイターを返却しに来たのだ。 皇帝は驚き、慌てて自ら謁見に応じて話を聞けるように手配した。 「皆、たいそう満足したと聞き及んでいる。機体を返却するのであれば、理由を申せ」 「それが……」小雀たちは顔を見合わせた。 話を聞いた皇帝はあっけにとられた。 そして、確かに自分は女を侮っていたと自覚した。 「分かった」と皇帝は告げた。「ストーキング ファイターは全て処分して一切、再生産しないと約束しよう」 そして、小雀戦闘機隊は安定し、末永くオルランド戦力の一角として有効に機能したという。 (遠野秋彦・作 ©2009 TOHNO, Akihiko) オルランドの全てが読めるお買い得電子書籍はこれ! 超兵器が宇宙を切り裂き、美女が濡れる。  全艦出撃! 大宇宙の守護者: オルランド・スペース・シリーズ合本
全艦出撃! 大宇宙の守護者: オルランド・スペース・シリーズ合本
|
|
||
|
|